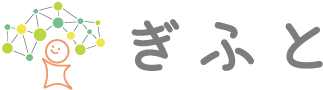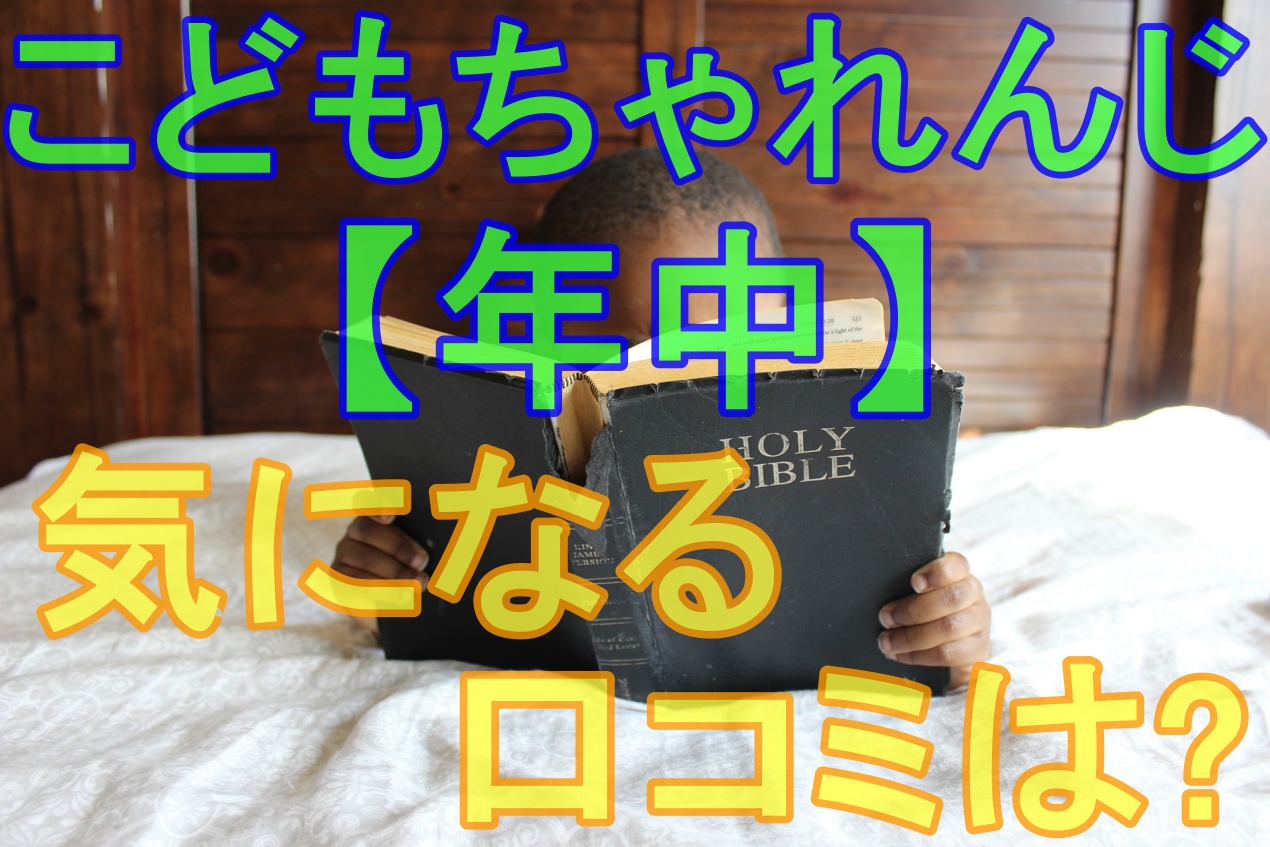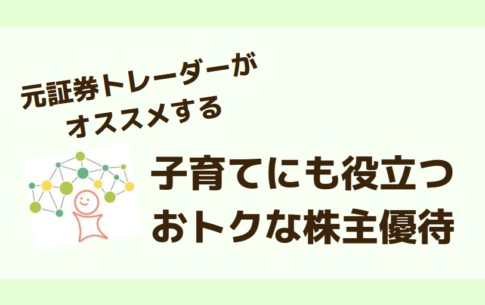ざっくり言うと
- 自閉症
- アスペルガー症候群
- ADHD(注意欠陥・多動性障害) など
- 子供が叫ぶのは、何かしらの理由がある。
- 子供の奇声(叫ぶ)は、親のせいではない。
- 子供の奇声=発達障害と思ってはいけない。
- 子どもの奇声は、年齢と共に減少していく。
例えばスーパーやレストランなどの、公共の場所で、急に「キーー!」と甲高い声を上げる子供がいたら、皆さまはどのように感じますか?
コミュニティサイトなど、世間の声を伺ってみると、「子どもの叫び声は、親のしつけの悪さが原因である」と考える方が、かなり多くいらっしゃるようです。しかし実際には、子供が叫ぶ理由は、単にしつけや育て方に問題がある訳ではなく、子どもの心身が発達していくうえで重要な意味を持っています。
本日は、子供の叫びの原因と、年齢別の対処法を、みなさんと考えていきたいと思います。
目次
子供が叫ぶ7つの理由
子どもたちが奇声を上げることには、そのときどき、子供の発達段階ごとにも、様々な理由が考えられます。
大人はその理由をくみ取ったうえで、適切な関わりを持つことが重要であると言えるでしょう。
それでは、子供が叫ぶ主な理由を見ていきましょう。
1:不快感があるとき、機嫌が悪いとき

おむつが汚れて気持ち悪いときや、お腹が空いてるときなど、不快感がある時に、奇声をあげることがあります。だって、気持ちが悪いんですもん。腹ペコなんですもん。
また、眠い時に機嫌が悪くなる子供は多くいます。


2:要求があるとき

抱っこしてほしい、このまま遊びたい、帰りたくないなど、赤ちゃんが何かしらの欲求を訴えるために、奇声をあげます。これは、その子供の現在何をしていたかで、原因が特定できます。



3:不安に思うとき

恐いことがあったり、親が近くにいなかったり、よくわからないけれど不安になるときってあります。すると、子供は奇声や大声をあげる場合があります。
また、知らない人や場所に対して、不安を感じて奇声を発する子供もいます。嫌がっているアピールだけでなく、大声を出すことで精神安定のため防衛本能が働いていることのあらわれです。


4:子供が言葉にできずもどかしいとき

2.3歳になると、ある程度言葉でコミュニケーションができるようになりますが、表現できない言葉もあります。言葉が話せないことで、もどかしい気持ちを表現するために、奇声をあげることがあります。
大人になっても、自分が相手に伝えたい言葉が見つからないときにモヤッとしますよね?大人はどうにか、言葉を見つけて対処できますが、子供は、まだ言葉力が未熟なので、感情に任せてしまうのです。


5:声を出すのが楽しい時

生後5~6カ月すぎると、聴覚が発達して、自分の声が認識できるようになります。そのため自分の声を聞くことが楽しくて奇声を発することが良くあります。笑顔で奇声を発している場合などはこのケースが当てはまるでしょう。
まだこの時期は、声量のコントロールがうまくできない時期なので、子供も、自分の声にびっくりした顔をします。これもまたかわいいですよね。

6:眠い・疲れたと感じているとき

夕方に奇声を発する場合は、1日の疲れが出てきたことや周囲が暗くなってきたことに、不安を覚えて泣くことが考えられます。(たそがれ泣きともいいます。)
また生活のリズムが一定でないと睡眠の質が悪く、それ故にストレスを感じやすくなることもあります。それによって、大泣きしたりする子供もいます。


関連記事↓
7:その他 障がいの可能性?

子供が叫ぶ理由には、気持ちだけではなく、病気や障がいが原因で、奇声を上げる子供もいます。大声や奇声で悩むママの多くは、「うちのこは病気?」「障がい児?」で悩むことが、かなり多いようです。
病気や発達障害を疑われるときは、早めに病院で受診をしましょう。
発達障害は、3歳までは判断しにくいです。
もし、5歳を過ぎても、奇声や大声がひどい場合は、迷わず病院で相談しましょう。早期発見、早期対処が今後の子供の社会生活を大きく左右します。
素人が判断することは非常に難しく危険なので、自分で判断してはいけません。大まかには以下のような可能性があるかもしれません。
年齢別の対処法
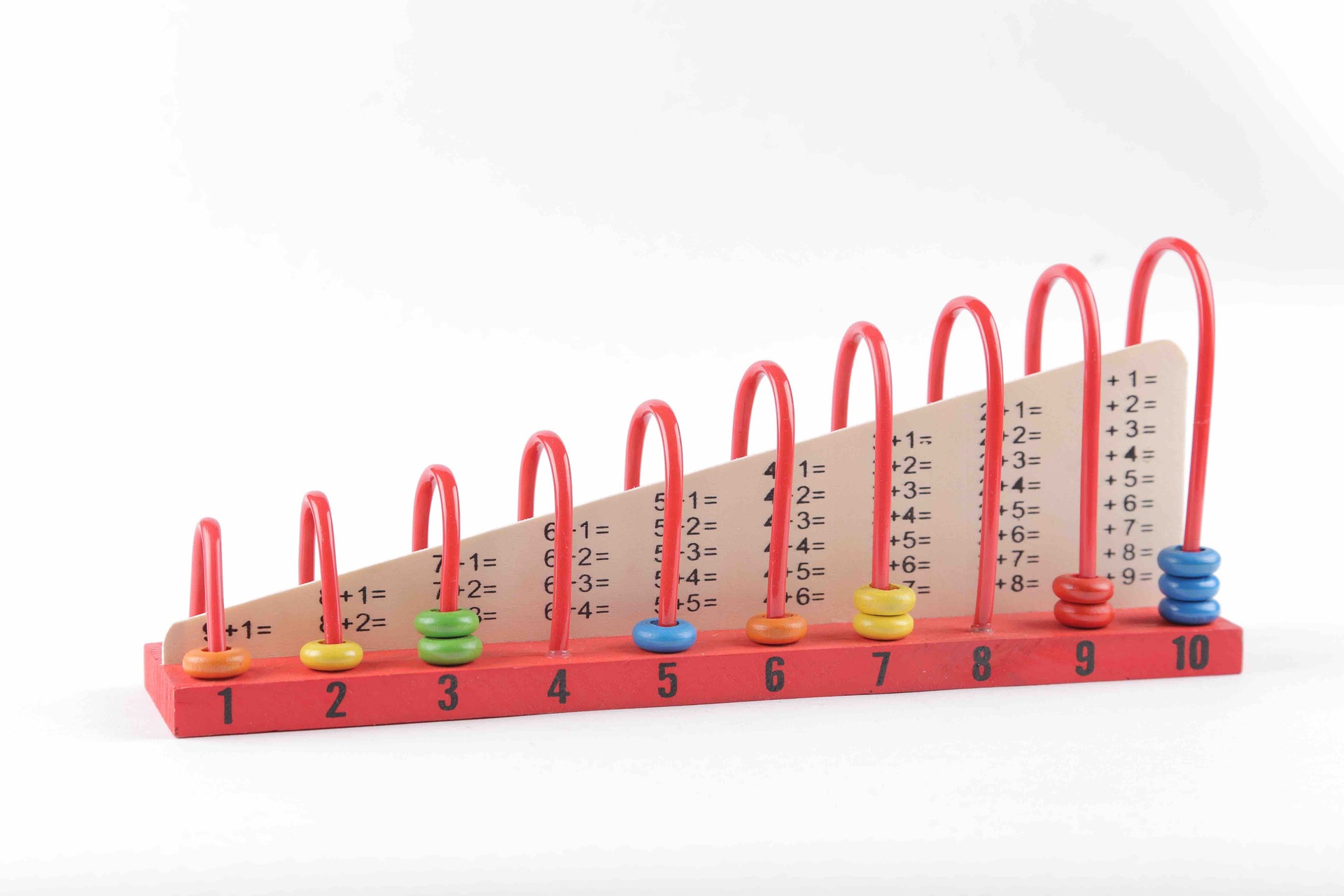
それでは、基本的な年齢別の対処法を挙げていきますが、これはあくまでも一般的対応法なので、この対応でうまくいかないときは、その子にあった対応を家族で模索して、導いてあげてください。
叫んだり、暴れたり、奇声を発したり、子供の数だけ理由があって、状況もばらばらです。それは、赤ちゃんでも大人になっても、同じです。そのとき、その子その子にあった対応ができる大人が、いるかどうかでその子の社会でのみられ方が大きく変わってくるのです。
0~1歳児が奇声を上げる原因・対処方法

このころは、体や言語の発達が未熟な乳児期および幼児期初期なので、泣いて表現するしかできないので、親の見る力が求められます。
要求したいことがあって叫ぶとき
乳児の時期は、自分の思い通りにならない場合でもそれをじょうずに表現できません。ミルクが飲みたい、おむつを替えてほしいなど、要求を叫ぶことによって表現します。
自我が発達し始める生後8か月頃には、自分の思い通りにならないと、怒りながら奇声を発することもあります。対処法としては、まず子供の気持ちになって、子供が、どんな気持ちなのかを考えましょう。
「お腹が空いたのかな」とか、「お尻が気持ち悪いのかな」とか、優しく声をかけながら接することで、子供も安心してきます。
子どもの欲求が満たされると、落ち着きます。それでも落ち着かないときは、ほかの原因も探しましょう。あとは、親が、ドンと、ゆったりした気持ちで、接することです。
不安になり叫ぶとき
知らない場所や知らない人に対して、戸惑いや不安を感じて奇声を発する子どもがいます。嫌がっているアピールだけでなく、大声を出すことで精神状態を安定させようと防衛本能が働いていることの表れでもあります。
そんなときは、子供のそばにいてあげるようにしましょう。
家事でどうしても手が離せないときもあると思います。しかし、10分でも良いので、子供の気持ちを落ち着かせることを優先させてください。
親がハグしてあげたりすることで、安心できます。どうしても気持ちが落ち着かない時は、おもちゃを与えたり、ビニールをこすり合わせる音など、落ち着く音を聞かせたりすることもおすすめです。とにかく、子供の不安を、察知して、安心されることが大事です。
疲れた(たそがれ泣き)と感じて叫ぶとき
夕方の時間帯に奇声を発する子供もよく聞きます。そんな時は、1日の疲れが出てきたことや周囲が暗くなってきたことに、不安を感じてます。
外が暗くなったら、早めに電気をつけましょう。そして、好きなおもちゃで一緒に遊んだり、抱っこしてあげたり、子供がリラックスできる環境を作る事が大事です。
夕飯の準備などで忙しいかもしれませんが、その時だけは、子供優先でかまってあげましょう。また生活のリズムが一定でないと、睡眠の質が安定せずに、ストレスを感じやすくなることも考えられます。
早寝早起きをこころがけ、親子ともども生活リズムを整えることで奇声が、減ることもあります。


声を出すのが楽しくて叫ぶとき
生後5~6カ月くらいたつと、自分自身の声が認識できるようになります。そのため自分の声を聞くことが楽しくて奇声を発することが良くあります。
そんな時は、声量のコントロールがうまくできない時期なので、口の前で「シー!」とジェスチャーをすることを繰り返し、奇声をあげる以外に楽しめる遊びを提示して気をそらしてあげると、自然に落ち着いてくるでしょう。
「シー!」のジェスチャーはすぐにはわかりませんが、繰り返すことで、ここでは大声を出してはいけないことを学び、徐々に声量を調整できるようになっていくでしょう。

注目してほしい・周囲の反応をみて叫ぶとき
誉めてほしいときや注目してほしいとき、奇声をあげた際の周囲の反応を楽しんでいるときなども奇声を発します。声を出すことによって、親が自分を見てくれるといううれしさの表現だと思います。そんなときこそ、メリハリある接し方をしてあげてください。ただただ、過剰反応するのは好ましくありません。
たとえば、子供から離れる際に「今から〇〇するからひとりで遊んでいようね!」などの声掛けをして、静かに待ってることができたら、過剰に誉めてあげると、だんだん学習していきます。


毎日の行動を習慣つけすることで、この時間は奇声をあげてもかまってもらえない、と自然に理解させることも大事です。
それでは、簡単に表にまとめます。
【叫ぶ原因と対処方法】
| 要求があるとき | やさしく声をかけながら、何を訴えているのかを考える。 |
| 不安なとき | ・子どものそばにいてあげる。 ・落ち着く音(音楽)を聞かせる。 |
| 夕方(たそがれ時)に叫ぶとき | ・早めに電気をつける。 ・おもちゃなどで、気を紛らす。 ・かまってあげる。 |
| 声を出すのが楽しいとき | ・基本的には、そのままでもOK ・あまりにも大きくなったら、「シー」を教える。 |
| 注目されたいとき | ・過剰に反応すると逆効果。 ・静かに待てた時こそ、過剰に褒めてあげる。 |
0~1歳児の奇声を予防する対策
生活リズムを整える
子供は生後6ヶ月以降にもなると、夜はまとめて眠れるようになります。早起き昼寝をちゃんとさせて、夜は眠るリズムを作りましょう。親が規則正しいと、子供は自然に生活のリズムをつけることができるようになります。
眠いときって、子供はイライラして不機嫌になりますので、精神面で安定させる為に生活のリズムを整えましょう。早寝早起きは子どもの体調を整えるので、ストレスも軽減させる働きがあります。
たくさん遊んでストレス発散
自分で歩けるようになったら、外遊びを沢山すると良いでしょう。外に出ることで、環境が変わりますし、活動量も増えます。あと、太陽の日差しを浴びることで、かなりのエネルギー消費になります。
いつも家の中で遊んでいると、飽きてきます。動き回れる行動範囲がせまいので、子供のストレスも溜まってしまいます。なので、外で体を沢山動かし、ストレス発散をさせましょう。
また体を沢山動かすことで、子供は疲れますので、夜ぐっすり眠ってくれます。。

「シー」のポーズをおぼえさせる
電車や、お店などでは静かにしないといけない場面があります。また、公共の場所でうるさくしていると、周りに迷惑です。しかし、子供は、この場所が静かにしないといけないなんて最初はわかりません。だから、家にいる時と変わらず同じトーンでお話しするし、走り回ろうとします。
だから、静かにしなければいけないことを子供にもわかるように、しつけていく必要があります。おもちゃで気を反らすのも1つの手ですが、「シー」とポーズを取ったり、「静かにしようね」と話しかけてください。
しかし子供は、「静かにしないといけないこと」をすぐ忘れてしまいます。なので、繰り返し「シー」のポーズをすることによって、子供も理解していくようになります。

2~3歳児が奇声を上げる原因・対処方法

2歳ごろなると自己主張も強く見られ、多くの子どもたちが「イヤイヤ期」に入ります。ここからは、ある程度は大人の言うことも理解できる2~3歳が奇声を上げる原因と対処法をご紹介しましょう。
2~3歳が奇声を発する原因
0~1歳の項目で挙げた他に、下記のような要因が奇声を発する原因になっていることがあります。
自己の発達が、急激にきますので、自分でやりたいこと、伝えたいこともとても多くなりますが、一方で体や言語の発達が不十分なために、それをうまく表現したりすることができないときもあります。
またまだ経験が浅く、どのように対応して良いかわからずに、そのストレスが奇声となって表れるケースをよく目にします。。


まずは、やりたいことがあれば、できる範囲で挑戦させてあげましょう。また、子供がうまくできなくて困ってるときは、状況に応じてそっと補助をしてあげ、できたところを褒めてあげましょう。それだけでも、達成感と褒められたという気持ちが子どもを安心させます。
上手に気持ちを表現できなかったり、感情の表し方がわからないなどで奇声をあげていたら、まずは「〇〇したかったんだね」「上手くいかなかったんだね、それは悔しかったね」など気持ちを代弁してあげましょう。抱き締めて気持ちを落ち着かせてあげることも大切です。
少し気持ちが落ち着いたようならば、「こういう時はこのようにすればいいんだよ」と具体的な方法を伝えてあげましょう。
また大声をあげてはいけないこと、それがなぜいけないかも根気強く教えていく必要があります。
注意を繰り返すことで、徐々に奇声を発する回数は減ってくるでしょう。毎日の積み重ねです。


4~5歳以降の奇声が見られたらどうする?

叫んだりすることが落ち着くのは、3歳前後です。しかし4.5歳になっても、奇声が出てしまう子供がいます。
何度言い聞かせても奇声がなおらない場合は、発達障害の恐れがあります。
成長には個人差がありますので4.5歳になっても奇声が治まらないからといって、必ずしも発達障害というわけではありません。発達障害は自己診断できることではないので、気になるときは、専門の病院に相談しましょう。
何科にいけば良い?と疑問に思う方もいるかと思います。小児科は子供の病気や障害を全般に扱っていますので、発達障害かもしれないと思ったら、小児科で相談しましょう。
子育ては、一人でやるよりみんなを巻き込もう!!
私たち親も小さいときに、愛情を持って、親や周囲の方に見守ってもらいながら成長してきたのです。自分が親になったからと言って、すべて、自分で行わなくてはいけないと、とても重苦しく考えてる子育て真っ最中の皆さん。一人ではないんですよ~。

みんなで、子育てを楽しく考えていける社会に変えていきましょう!!一人じゃないいんだから、みんなで子どもと向き合えばいいんです。その気持ちは、必ず子供に伝わります。
お勧めの記事↓
まとめ
確かに子どもの奇声にはそれぞれ理由があり、どうすることもできない部分もありますし、あらかじめ防ぐことが難しいものです。突然、公の場で鼓膜が破れるような奇声が聞こえたら、ビックリしたり「うるさいな」と感じてしまったりするでしょう。それは子どもとあまり関わわることがない方にとってはごく自然な反応です。
しかし、周りへの配慮を怠って「子どもだから仕方ない」とするのは、余計に反感を買うことであり子どものためにも良くありません。 子どもが奇声をだす原因をしっかりと理解し、気持ちに寄り添いながら、周りの人に気を遣う。
そしてこどもにちゃんとした態度をもって「ここは大声を出すべき場ではない」ということを教えてあげることも大事なことです。子育てに関わる者にとっては、ストレスが溜まりやすいですが、ある程度長期的視点を持って、ゆっくり対応していきましょう。
それでは、かわいいわが子と楽しい育児ライフを送ってくださいね。