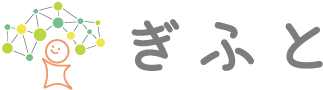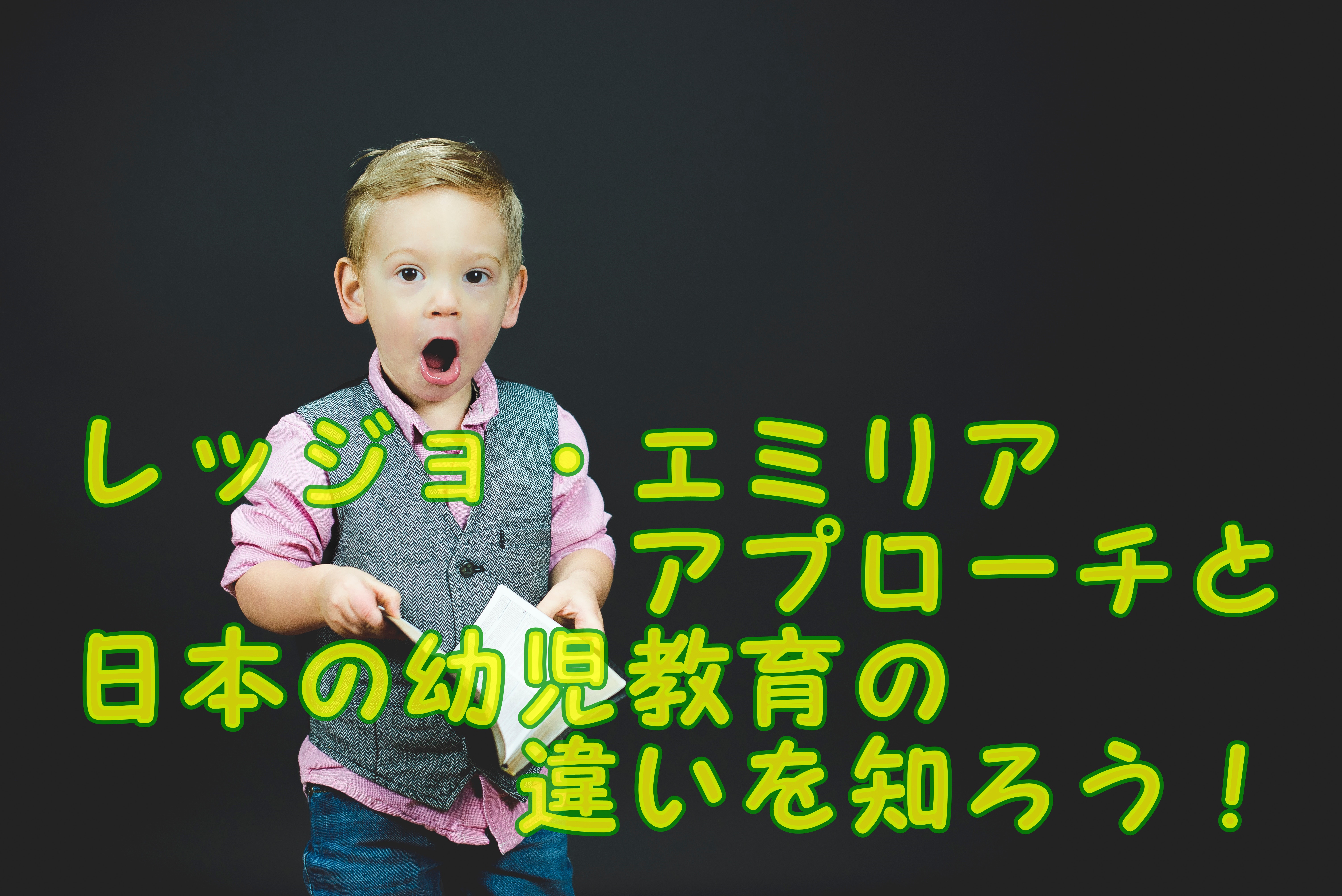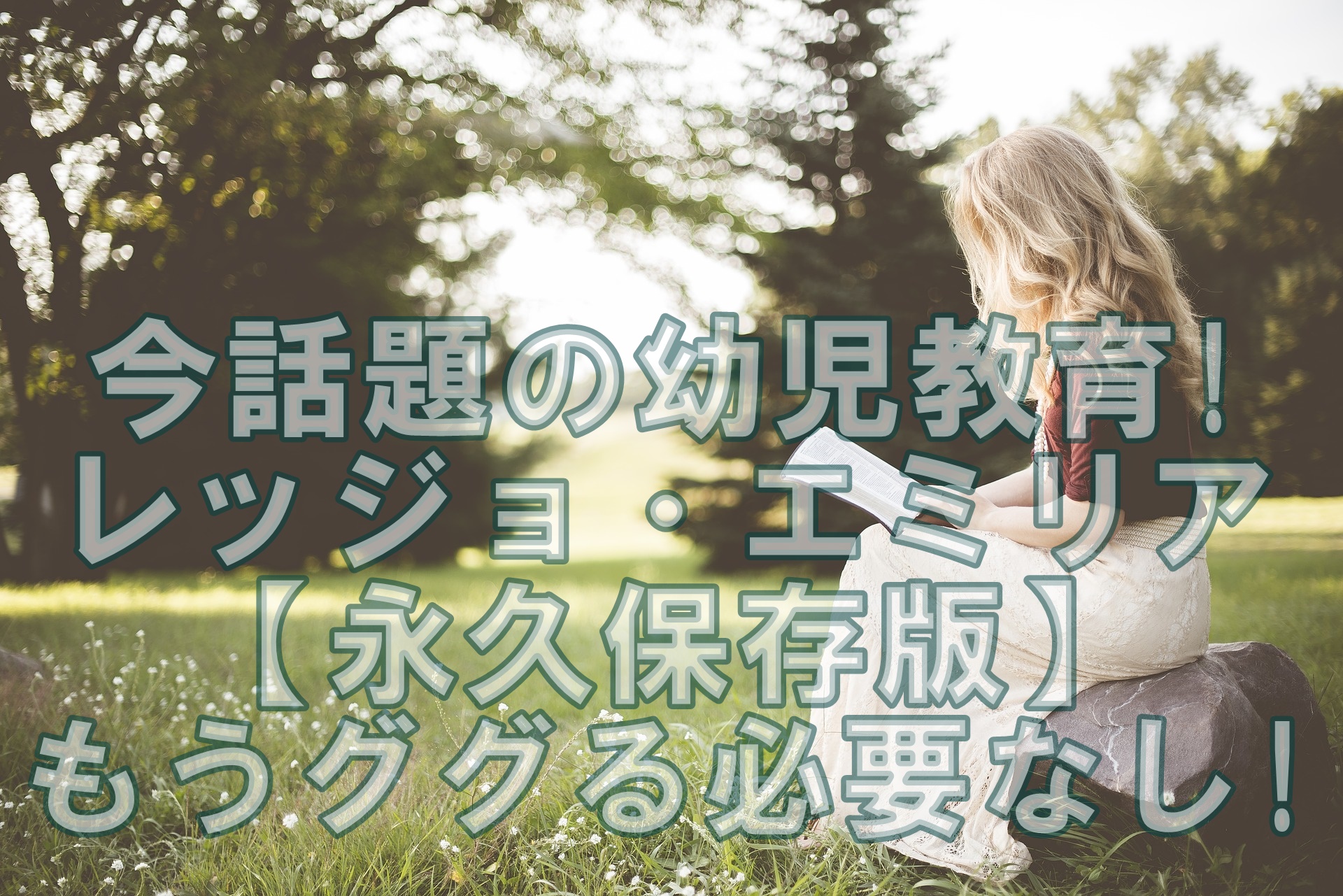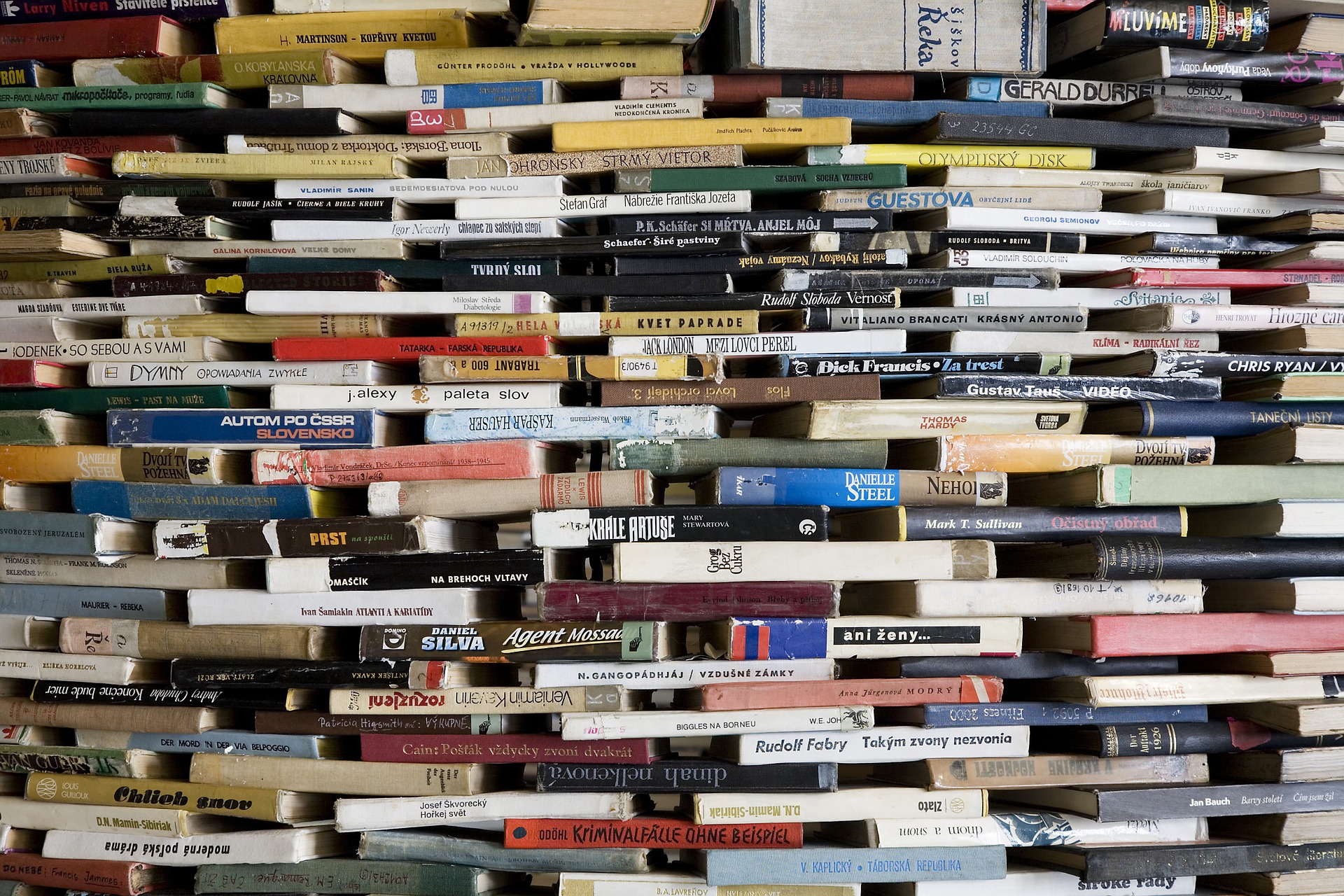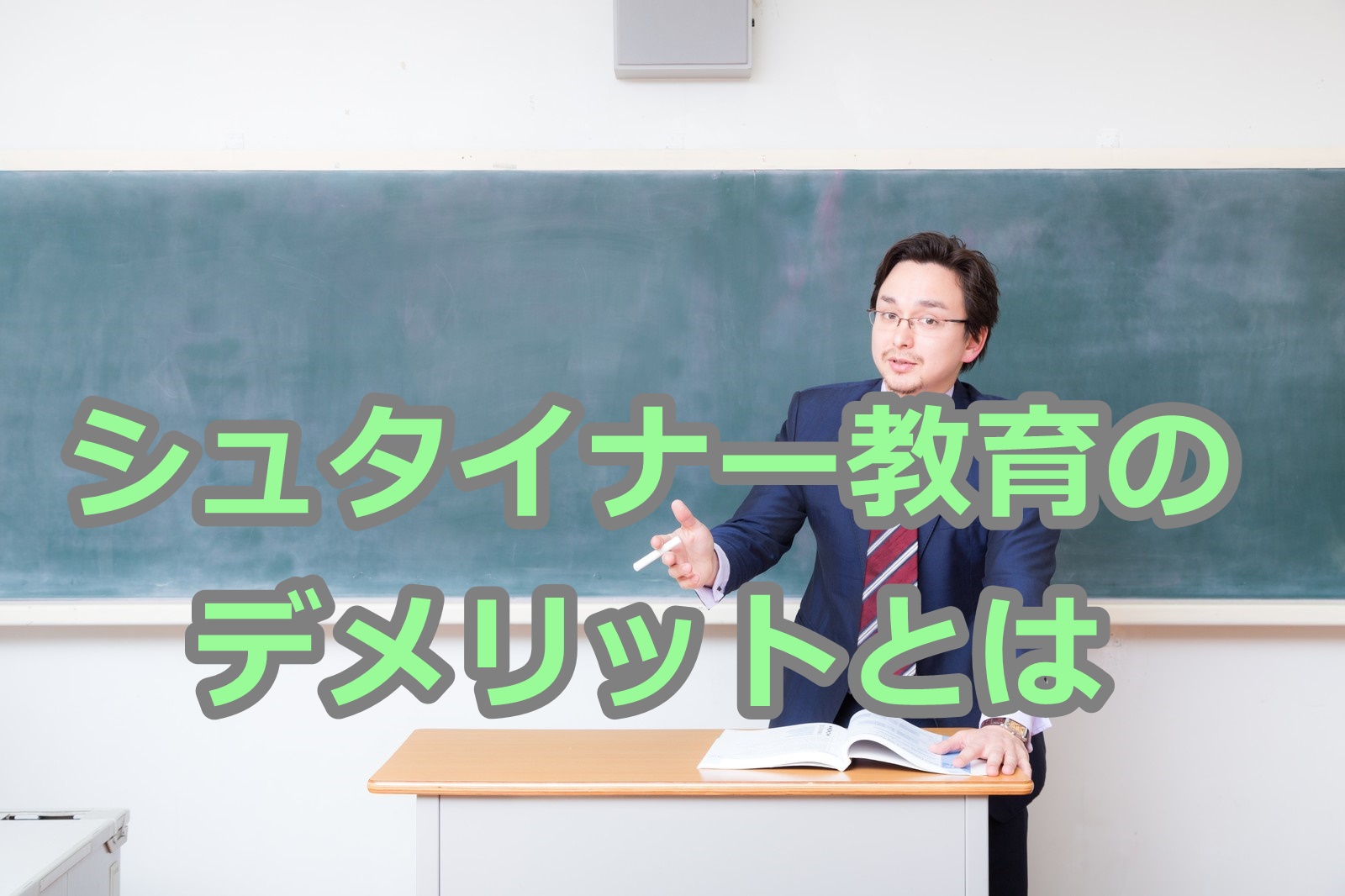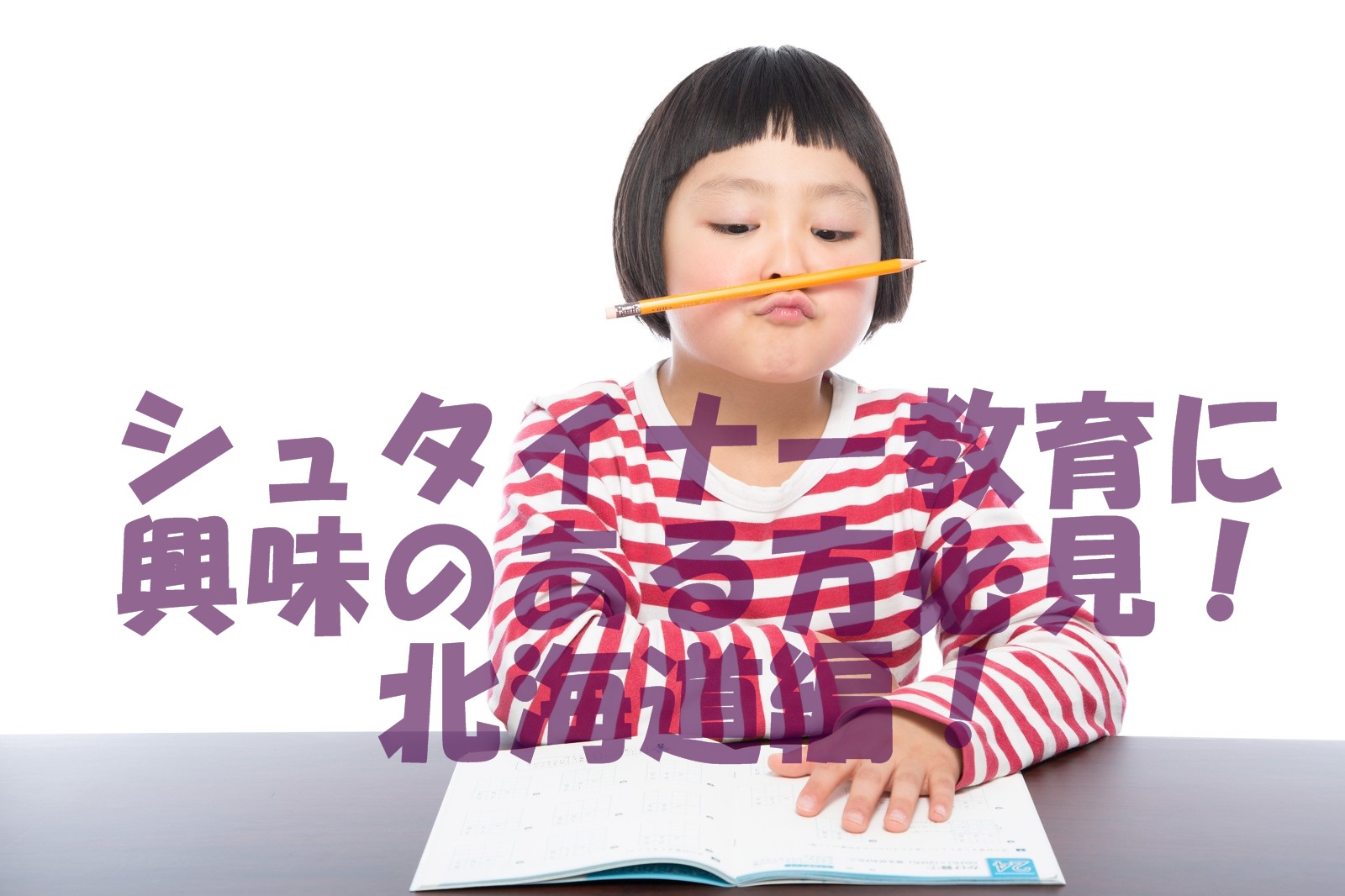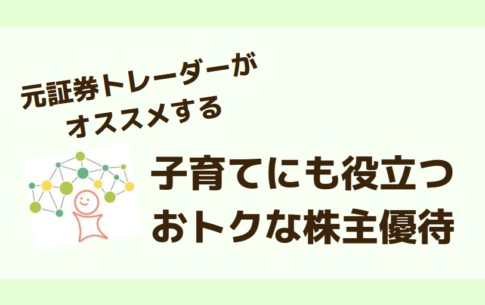ざっくり言うと
- 子供の想像力や感性をアートで表現させる。
- 子どもが主体となってプロジェクト活動する。
- ドキュメンテーションで子供も成果を振り返る。
- 創造性を育ませるためのアトリエや広場がある。
- 自分で考えて行動することが自立性に繋がる
- 話し合うことで協調性が育まれる
- 子供と話し合う機会を増やしていく。
- 牛乳パックや段ボールなど、廃材を活かして芸術的な感性を磨く。
- コルクボードやホワイトボードを使い、ドキュメンテーションコーナーを作る。
- 「今日はこれを作ろう」と提案はしないこと。
- 「これらを使って、何か好きなものを作ろう」と声をかけてある。
- 「子供自ら考えてもらう」
- 異国の軍隊により占領に抵抗するレジスタンス運動
- 女性差別がなくなり、女性の参政権が認められ、女性が大活躍するフェニズム運動
- レッジョエミリア教育……レッジョエミリアアプローチ
- モンテッソーリ教育……モンテッソーリ・メソッド
- 0歳から7歳
- 8歳から14歳
- 15歳から21歳
- 同じ教科を1週間から集中的に学ぶ「エポック授業」
- 体を使ってさまざまなことを表現する「オイリュトミー」
- 線を描くことで物の形を理解する「フォルメン」
- 戦争後の厳しい環境のなかから生まれた子どもたちの未来を思いやる教育
- レッジョ・エミリアアプローチの実力は世界に認められている
- レッジョ・エミリア市民は幼児教育の重要性に気付いている
- 子どもたちの記録方法が最新で無駄がなく、次の学びへ活かされている
- レッジョ・エミリアでは人として重要な自主性・協調性が身につく
- 子どもたちの個性にスポットライトを当てた教育を実践している
初めてレッジョ・エミリアという言葉を聞いた時、何だその魔女みたいな名前は・・・と思ったのが私の正直な感想です。
その名前がイタリアの地名であることはおろか、まさかレッジョ・エミリア・アプローチが幼児教育においてこんなにも重要で世界から注目されているものだとは知りませんでした。
調べていくうちにその魅力に圧倒されつつ、日本の教育事情についても現状の一部を知ることができたので、これはぜひ皆さんにも知っていただきたい!と思ったので早速ご紹介していきたいと思います。
目次
レッジョ・エミリア教育とは
レッジョ・エミリアアプローチの始まりと日本の教育の歴史

レッジョ・エミリア教育のことの発端は第二次世界大戦終戦直後、1945年のことです。悲惨な戦争により瓦礫の街と化したレッジョ・エミリア市でしたが、人々は子どもたちへの将来の希望を捨ていなかったことから始まります。
当時のレッジョ・エミリア市民は、戦争で破壊された建物から資材となるものを集めたり、軍が残した戦車や軍事用車両をスクラップしそれらを売り学校を建てる資金として活動していました。
こういった人々の活動を見て心を動かされた教育者や専門家が一体となり、「すぐれた人材を育てるには、まず乳幼児から」という理念のもとにレッジョ・エミリアアプローチが発足します。
その専門家たちの中には有名な絵本作家や演劇系の人などが集まったことから、「個々の個性や表現を大事にしていきたい」という特色を込めた幼児教育が考え出されました。
そして1963年に最初のレッジョ・エミリアアプローチの希望を込めた幼児学校ができたんですね。

ちなみに日本が現在のような小学校~中学校までの9年制の義務教育になったのが1947年のことであり、1948年に保育要領が制定されました。
しかし、この当時の日本の幼児教育では「しつけ」に重点を置かれていたとも言われ、先生がいかに子どもを正しく指導しその子どもの発達を促すかという指導目標があったようです。
レッジョ・エミリアアプローチの「個々の個性や表現を大事にしていきたい」という考え方と真逆だったようですね。
世界で注目されはじめたきっかけ

みなさんは「ニューズウィーク(Newsweek)」という雑誌をご存じでしょうか?名前だけであればなんとなく聞いたことがあるという方もおられると思いますが、私もその一人です。


ニューズウィークはニューヨークの本社をはじめアメリカだけにとどまらず、国内外に22の支局を持ち世界各国でそれぞれの国の言語に翻訳されています。
レッジョエミリア教育では、一人ひとりの個性を尊重するために一体どのような教育に取り組んでいるのでしょうか。レッジョエミリアの特徴を簡単にまとめてみました。
レッジョ・エミリア教育の特徴
特徴1:想像力や感性をアートで表現する

レッジョエミリア教育の最大の特徴は、子供の感性を表現しやすいのは「アート」だと考えています。なぜ、想像力を「アート」で表現させているのか。理由は、子供が楽しく取り組みやすいから、というものあると思います。
そしてこの、アートを推す理由として、時代背景が大きく関わってきます。
レッジョエミリアはもともと戦争でボロボロにされた街だったため、教育できる環境が整っていませんでした。それでも、子供たちの教育環境を何とかして整えてあげたい。そんな人々の思いがあり、今ある材料や道具を使って何か出来ることを考えました。
この教育法を始めたローリスマラグッツイも、出来ないことを考えるのではなく、出来る事に目を向けて才能を伸ばしていくべき、という考えを持っていました。
人々が皆で協力して考えます。戦争でボロボロになった街で何もない中、一体何が出来ると。
とても気になりますよね。
目を向けた物は、戦争でボロボロになったゴミになるはずのもの。鉄くず・リサイクルごみの廃材・自然素材などです。
この、ゴミだと思われるものが活かせるものとして考え、沢山この材料を使ったのです。今ある材料でできるのがアートだと考えたということに、人の考える力はすごいな、と思いませんか? レッジョエミリアの原点はここだったのですね。
子供たちの教育に、大人たちが一つになって、子どもたちの表現したい気持ちを自由に表現できる環境に整えたのです。
私はこの話を知り、みんなで真剣に取り組み、考えたからこそできた教育方法であり、改めて人々の力の凄さに感動しました。この歴史があってこのレッジョエミリア教育は誕生したのです。



実はアートといっても、絵を描くだけがアートではありません。
実際に自然の葉っぱを触る・目で見る・触れて感じる。それもレッジョエミリア教育ではアートとしています。
この自然に触れて、自分で感じたことを芸術で表現することが個性にも繋がっています。
このアートによって子供の想像力や感性で個性を出させていることがよくわかります。ですが、これだけで個性が尊重されているわけではありません。他にもたくさんの教育環境が用意されています。



特徴2:主体的にプロジェクト活動をする

通常の教育では、大人や学校の先生が大体の内容やテーマが決まっている中で、子供たちがその指示に従い、一緒になって行動します。そのような教育が日本では一般的だと思います。
レッジョエミリア教育では、このようなことはしません。
大人が子どもに一方的に教えるようなことはせず、大人は子どもの持っている能力を信じて、子どもと大人が一緒に学んでいくことを大切にしています。その代表的な活動に、「プロジェクト活動」というものがあり、それに取り組んでいます。
では、この「プロジェクト活動」とは、一体何なのでしょうか?
プロジェクト活動とは、一つのテーマを決め、長くて1年間という長期間に渡り、子供たちが主体となって考えながら、「工作」や「お遊戯会」などの活動を行います。
ですが、これを聞いて子供たちだけで本当にできるの? って思いませんか?
これを実際に行うには、子供一人ひとりが尊重されるよう、大人が優しく見守ることが大切です。レッジョエミリア教育では、子供は一人で単独で行動するわけではなく、大体4人~5人を一つのグループにして議論しやすいようにしています。
しかし当然のことながら子供同士となると、どうしても喧嘩や討論など何か問題が起きるかもしれません。

ですがその喧嘩や討論を、レッジョエミリア教育では歓迎して見守っています。そして、この議論を見守っているのは保育士だけではなく、保護者や地域の方も一緒の仲間となって見守っていきます。
親としては、つい喧嘩が入ってしまったりすると仲裁に入ってしまいますよね。親もここは我慢の精神が必要になるかもしれませんが、この思い通りにならなかったことが起きることで、自分の感情をコントロールする力を身に着けていきます。
「プロジェクト活動」の時、親も保育士も地域の人も「チームの仲間」として見守ることが大事になります。
親や大人が見守ってくれている。そうすると子供は「自分は愛されているんだ」と感じることができ、自信に繋がり、安心して討論や意見を言える環境になっているのです。また、子供たち一人ひとりが自分の意見を話し、そして子供たちは友だちの意見を聞きます。そうすることで「コミュニケーション」が出来るようになっていきます。
小さな子供達でも、コミュニケーション能力が身についていくようになっているんですね。
そして他にも、「自立性」や「協調性」が育まれていることにも繋がっています。
子供の能力はすごいですよね。大人よりも心が何倍も一年で大きく育ってしまうことに、私は子育てをしていて日々感じてしまいます。
レッジョエミリア教育ではこの子供の成長能力を、もっと伸ばしやすくしようと研究された結果が出て、このように有名になってきたと思われます。






特徴3:ドキュメンテーションで成果を振り返る

保育園や幼稚園は、親が先生と連絡ノートを介して成長を確認することがほとんどだと思います。そして、毎日時間割等が決まっていたりするのが通常の教育環境ではないでしょうか。
レッジョエミリア教育では、子供の毎日を記録するのに使われているものがあります。それはメモ・動画・録音などを使って記録を残していきます。
この毎日記録することで、子供たちは今、何に興味を持ち、どんなことに触れたいのか、そして今日学んだことを親が確認し、知ることができます。
そして、この記録ですが、大人が把握するだけではありません。大人が確認している姿を子供たちも見ているのです。
大人が見ていてくれることで、子供たちは「自分は大人にとって価値がある存在であり、日々自分が取り組んでいることは大事なことである」ということを肌で感じ取ることができます。そうすると、自然と自分の成果も振り返るようになるのです。
このことをレッジョエミリア教育では「ドキュメンテーション」と呼んでいます。
通常の教育では、出来上がったものを展示し発表することがほとんどですが、完成された作品について、出来上がるまでの経過が説明される機会は少ないと思います。確かに出来上がった作品を展示し、見せることも大切なことです。
しかし、このドキュメンテーションは出来上がったものだけではなく、出来上がるまで学んできた過程をメモや動画に残していくのです。
子供を見ながら記録を残すというのはなかなか大変なことだと思います。ですが、先生たちはノートに細かく言葉や絵を描いてみたり、些細な表現を見逃さないように研修などにも参加し、力を身につけます。

もしかしたら自分達が、子育てで見逃してしまったようなことがいっぱいあるかもしれません。ですが、このドキュメンテーションは家庭でも取り組めることが出来ます。
子供の興味のあることを些細なことでもいいので、日々記録するだけでも学びに活かされると思います。これは家族でマネをしてみたいなと感じます。



特徴4:想像力を育ませるためのアトリエや広場がある

レッジョエミリア教育では、先に記述したように美術を中心に行い、「アート」で感性を表現しています。
その「アート」を表現するのに、子供が過ごす環境はとても大切であり、環境は「第3の先生」と考えているくらい重要視しています。その為にレッジョエミリアでは2つの環境を設備しています。
レッジョエミリアの保育施設の一つ。
芸術活動に必要な色鉛筆や折り紙、影絵遊びや万華鏡や鏡。自然の材料や光を楽しむことが出来る様々な道具などの、多種に渡る工具や材料が置かれ、子供たちの作品なども並べられて置かれている。
また、パソコンだったり本格的な楽器など、絵画や工作以外のものも置かれている。
芸術に関係するものを置いていき、思いついたら即行動できる環境になっているんですね。
子供たちが自由に行き来できる共同の広場になります。これはどこの学校でも必ず場所が決まっています。
イタリアの都市のスタイルは、広場を中心に広がっており、その広場には噴水や市場が栄え、人が集まるスペースとして設けられています。レッジョエミリアの施設も、それに影響したものと思われます。
レッジョエミリアのピアッツァもまた、イタリアに住む人たちの習性の現れなのかもしれません。
そして、レッジョエミリアを支える専門家が存在します。
アトリエリスタ(芸術の専門家)とペタゴジスタ(教育の専門家)という方々です。
まず、子供たちと密接に関わっているのがアトリエスタですが、この関わり方は、現代の育児、教育においても、必要なものだと思われます。
さて、何をしていると思いますか? レッジョエミリアの教育環境らしいなと、とても感じる方々も多いと思われます。
アトリエリスタは、決してスキルを教えたりはしません。
通常の教育だと「なぜこうなるの?」という質問に、大人は教えてあげたりすることが多いと思います。ですが、レッジョエミリア教育では、子供の探求心を大事にさせるため、ただ見守り、答えを言いません。
では、子供が「答えはこれでしょ?」って訊いてきたらどうでしょう。普通なら、正解。残念。など、○×の判断を下す場面が多いと思われます。
しかし彼らは違います。もしそのような場面を迎えた場合アトリエリスタは「じゃあ、次はどうする?」と子供に更に実験させるよう、次の問題に向き合わせる様にするのです。
そうです。アトリエリスタは、この子供達の探求心を触発させ、興味津々に研究し、色々なひらめきと個性が開花しやすい時を見逃さず、子供が感じたもの、そのすべては答えとして受け止め、一人ひとりの個性を尊重させる役割を担っているのです。






続いて、ペタゴジスタ(教育の専門家)の説明をさせて頂きます。一体どんな方々がペタゴジスタになっているのでしょうか。
ペタゴジスタは、大学で教育学を専攻された経歴を持っている方々です。
教室での実践を、教育や研究と結びつけていくようにしており、いくつかの園を統括して受け持つことで、教師と親が協力し、子供の教育環境を整える役割をしています。
このペタゴジスタが、親や地域の人との繋がりを大切にし、コミュニケーションを取り合える環境を作ってくれていることでこのレッジョエミリア教育が成り立っています。
このアトリエリスタとペタゴジスタの存在がなければ、レッジョエミリア教育は成り立たないことであり、素晴らしい教育環境が出来上がったのは、このプロの方々の力も素晴らしいからなのだと思います。
レッジョエミリア教育の世界を、この本をご覧になれば、もっと驚けると思います。
レッジョ・エミリアに欠かせない「100の言葉」

レッジョ・エミリアアプローチをお話するうえで切り離すことができない次の詩をみなさんはご存じでしょうか?
子どもには
百とおりある。
子どもには
百のことば
百の手
百の考え
百の考え方
遊び方や話し方
百いつでも百の
聞き方
驚き方、愛し方
歌ったり、理解するのに
百の喜び
発見するのに
百の世界
発明するのに
百の世界
夢見るのに
百の世界がある。
子どもには
百のことばがある
(それからもっともっともっと)
けれど九十九は奪われる。
学校や文化が
頭とからだをバラバラにする。
そして子どもにいう
手を使わずに考えなさい
頭を使わずにやりなさい
話さずに聞きなさい
ふざけずに理解しなさい
愛したり驚いたりは
復活祭とクリスマスだけ。
そして子どもにいう
目の前にある世界を発見しなさい
そして百のうち
九十九を奪ってしまう。
そして子どもにいう
遊びと仕事
現実と空想
科学と想像
空と大地
道理と夢は
一緒にはならないものだと。つまり
百なんかないという。
子どもはいう
でも、百はある。
子どもたちの100の言葉(レッジョ・エミリアの保育実践について)田辺敬子 訳
私たち大人は歳を重ねるごとに様々な経験をし、世の中のある程度のことを平均的に自分の知識や学びとして習得していると思います。だから、子どもたちが何かを疑問に思った時、すぐにそれに対して答えてしまうことができます。
これは決して悪いことではありません。ですが、その答えは時に子どもたちの創造性や想像力を妨げてしまう可能性もあることを、レッジョ・エミリアアプローチの第一人者であるローリス・マラグッツィは懸念しています。

日本でも「十人十色」という言葉があるように、子どもたちが得意・不得意とすることは当然違います。これに対し日本では不得意なことも克服させ平均的にその子の力をアップさせようとする傾向にあります。
一方レッジョ・エミリアアプローチでは、「子どもひとりひとりの意思、個性を尊重し、伸ばす」という教育理念を基に、子どもたちの興味や必要性にそったカリキュラムが作られ、楽しんで学べる教育を大切にしているんですね。

自宅で出来る、レッジョエミリア教育法

最近、レッジョエミリア教育は話題にはなってきていますが、さぁやってみよう。そう思っても、一体どのように取り組んでいったらいいのかわからないですよね。
近くにレッジョエミリア教育を取り組んでいる場所、日本ではあまりなく、学校も数が少ないのが現状です。


これは親と子のコミュニケーションにもつながる大切なことでもあります。では、自宅で取り入れていくにはどのようにしたらよいのでしょうか。
まず、大まかに分けて三つとなります。
全部する必要はなく、何か一つだけでも取り組んでみる。というのもいいと思います。
では、どのように家庭で取り組んだら、レッジョエミリア教育に繋がるのか。
レッジョエメリア教育法・子供と話し合う機会を増やしていく。

これは普段でも取り入れやすいですね。人にとって大切なコミュニケーション能力はこれで身につくのではないのでしょうか。
話し合う内容ですが、難しく考える必要はありません。日常の会話で十分です。例えば、出かけるときには「どこにお出かけする?」と聞いて、さりげなく子供自ら考えさせるような質問をします。
子供が「公園に行きたい!」そう答えたら「何を持っていく?」「何して遊ぶ?」という風に、どんどん質問し子供が考えれるように工夫をしてみましょう。
ここで大切なのは親が主導権を握るようなことはせず、子供を見守り子供が答えを出すまでじっくり待っていてあげることが大切です。もし、どうしても見つからない場合は助言を少し加えてみてもいいかもしれません。
会話の答えは子供が見つけるような工夫を心掛けましょう。






さておき、このような本をご覧になって、話し合う機会と、家庭内での育児に役立つ知識を取り入れてみるのも、良いかもしれません。
では続いて、工作の教育法となります。
レッジョエメリア教育法・牛乳パックや段ボール等廃材を活かして芸術な感性を磨く。

レッジョエミリア教育といえば、「アート」ですね。
アートは子供の感情表現を出すのに重要な役割をしています。日頃からいろいろな物に触れたり、廃材になってしまうようなものも、自分で考え、表現させましょう。
これらの心構えが大切となります。
ここからは、動画で工作内容を紹介していきます。まずは牛乳パック工作からです。
子供でも簡単にできるお手軽工作になります。
続いては、ちょっと不思議に見える。万華鏡工作になります。
インスタグラムにも、いろいろあがっているのでチェックしてみてください!
続いては段ボール箱工作です。
ちょっと複雑だけど、出来たら楽しいこと間違いなしですね。
冒険もので定番の宝箱。中身は大事なおもちゃ(宝物)を入れてみよう。
こちらもインスタグラムでもみんな色々作ってます。
色々紹介しましたが、何をどう作るのも、子供の自由です。
しかし、刃物類の使用は注意してください。これも万国共通です。
レッジョエメリア教育法・コルクボードやホワイトボードでドキュメンテーションコーナーを作る。

子供自身や親が子供の成長を見守る重要なドキュメンテーションコーナーを作ります。
簡単なのはコルクボードやホワイトボードで作ることです。リビングが家族みんなの集まる場所なので、一番お勧めです。
写真や記録がいっぱいになってしまって大変という方なら、タブレットやフォトフレームもおすすめです。家族みんなが子供の成長を見守ること、そして、母親だけでなく父親や兄弟、家族みんなが見ていてくれていると感じてもらうことで、子供も安心する環境になると思います。
ボードの活用は、インスタグラムでもあげられるほど色々あります。
ちょっとほのぼのだけど、子供はお手伝いを褒められると、凄く嬉しいと思います。
いろんなものを書いたり張ったり、幼児はなんでも遊びです。
用途が様々なホワイトボード・コルクボード。ぜひ取り入れて、遊びにコミュニケーションに活用してみて下さい。
家庭でも簡単に取り組んでいけるレッジョエミリア教育。少しでも興味がある方、もっと知りたい方はこのような記事もあります。
レッジョエミリア教育ができるまでの歴史
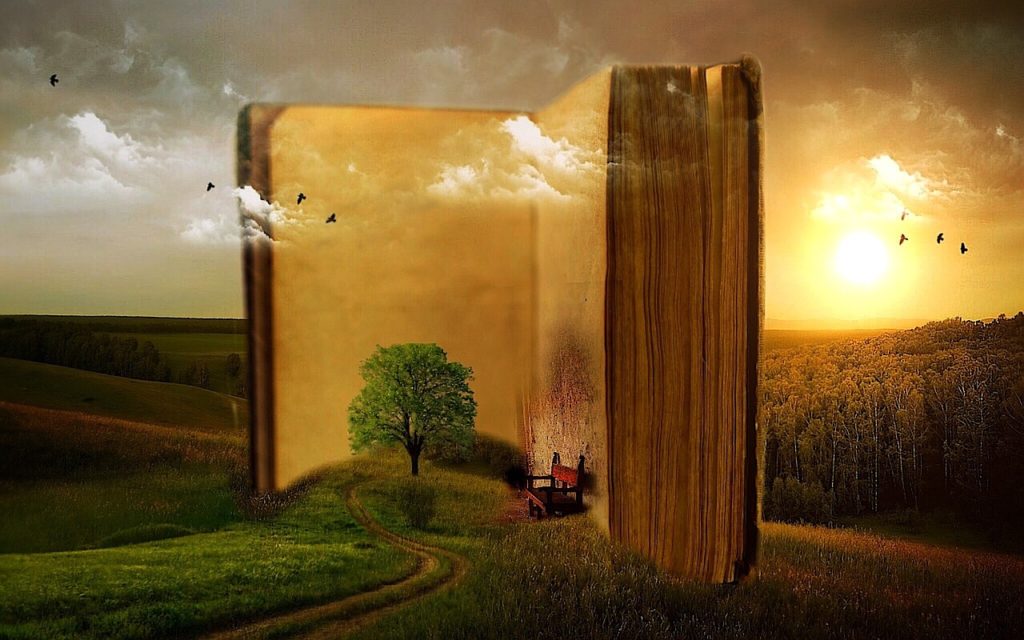
レッジョエミリア教育について、こんなに注目が集まったのはなぜなのでしょうか。これには、レッジョエミリアの歴史にも注目されているからです。
「レッジョ・エミリア」は、第二次世界大戦後の復興のなか、戦争でボロボロになってしまった町に、皆の力で学校を造ったことからはじまります。
教育の発起人は、郊外にある村ヴィラ・チェラで、教育者ローリス・マラグッツィの指導により開花しました。
この時代の社会では、
この二つの運動が目立っていました。
ファシスト政権の開放により、マラグッツィは人々に宗教色の持たない、新しい学び場を人々に求めさせました。当時の教育理論との統合・レジスタンス運動、フェニズム運動との連携などをしつつ、アートを用いた子供たちが自ら思考や感情を表現できる教育手法を編み出して来ました。
フェニズム運動の影響もあってか、多数の女性がレッジョエミリア教育に取り組んだことにより、大きく発展していきました。
1963年、イタリアで初の公立幼児学校ができました。

現在、レッジョ・エミリアの保育施設は18施設、幼児教育施設は51施設ですが、少しずつ増えつつあります。
1991年、「世界で最も優れた10の学校」に選ばれた学校が、この教育法を実践していたことから、世界的に有名になりました。
この世界で最も優れた10の学校、これに選ばれたというのが世界中で大きく反響を呼び、注目されたのです。






レッジョエミリア教育の歴史をしっかり勉強するなら、こちらをご覧いただくのも良いと思います。
レッジョエミリア教育で大切にしているのは。


レッジョエミリア教育では、「一人ひとりの個性を尊重させる」ということを大切にしています。この教育の創立者、ローリス・マラグッツィが書いた詩の中である「子供たちの100の言葉」では、
「子供には100の言葉があるが、99の言葉が失われないようにしなければならない。99を奪う教育ではなく、100あるものをすべて受け入れる教育にすることが大切である」
と伝えています。
個性を奪う環境ではなく、個性を尊重しなければこの100あるものをすべて活かすことは出来ないと考えました。
子どもが100人いれば100通りの考えがあり、それは100通りの表現の仕方だってあると思います。そして、その100通りのすべてを肯定するのが教育のあるべき姿だと考えています。
ですが、今の教育環境ではそれを否定してしまうのではないかと考えられています。実際に大人になると、社会で生きていくのに個性が出しにくく、失われやすくなっているように感じます。
教育に間違っている、正しいという考えはありません。
ですが、何より子供がどのような環境なら一番幸せで、過ごしやすく成長できるのか、それを考えてあげるのが親の役目だと思います。その為に、この子供たちひとり一人の個性を尊重させることができる教育環境をしっかり整えることが、重要だと思われます。



モンテッソーリ教育・シュタイナー教育との違い

ヨーロッパの幼児教育では、「モンテッソーリ教育」や「シュタイナー教育」が有名です。
歴史を見てみると、レッジョエミリア教育は第二次世界大戦後に誕生していますが、モンテッソーリ教育、シュタイナー教育は、第二次世界大戦前に生まれた教育で、歴史も長く、現在も強い人気があります。
レッジョエミリア教育とモンテッソーリ教育
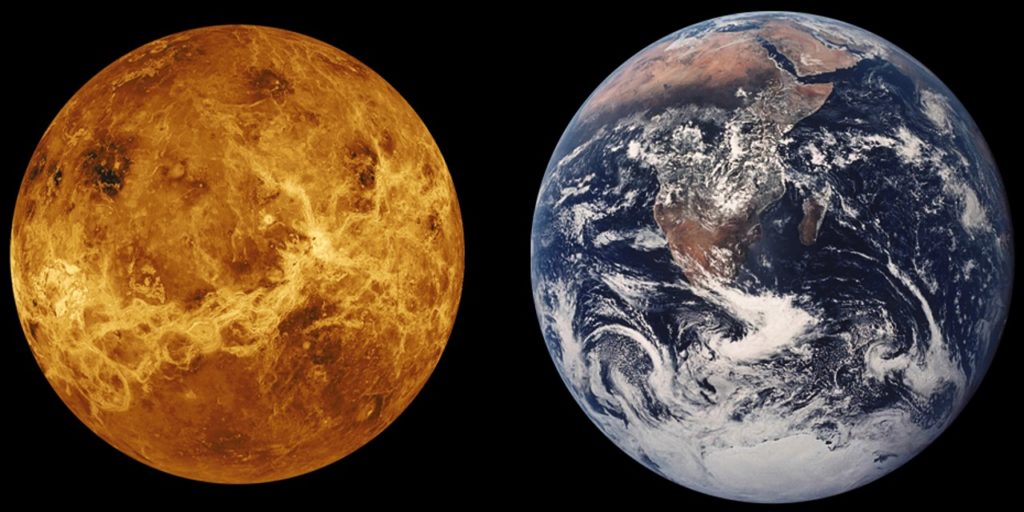
教育科で医師でもあったマリア・モンテッソーリが考案した教育方法です。
この教育の理念・目的は、
自立していて、有能であり、責任感と他人への思いやりを持ち、生涯学び続けるという姿勢を持った人間に育てる事です。
では、レッジョエミリア教育とモンテッソーリ教育はどう違うのでしょうか。

当然、このようになってしまいます。
「メソッド」「アプローチ」聞いたことはあると思いますが、意味は何だか分かりますでしょうか。

ではまずメソッドからです。意味は、方式・方法を指す言葉です。
モンテッソーリ教育には、既にカリキュラムがあり、子供たちはそのカリキュラムに自信を持って取り組み成長し、彼らが学習することで自立するようにしています。そこには慎重に選ばれた、おもちゃや書籍、子どもの自立を奨励するための教材が整えられています。
このように方法が決まっているモンテッソーリ教育では、個人それぞれが、自分のペースで進歩することができるようになっているんですね。
一方、アプローチとは、近づく事。を意味します。
先で記載した様に、レッジョエミリア教育では、周囲の大人も含め、集団で学び合って成長する、教育に繋がることに近づいていくという事を重視しています。
こちらの教育の方針も、子供の自立を考えた素晴らしい教育です。そんなモンテッソーリ教育について、もっと詳しく見てみたい。そういった方々には、こんなおすすめ記事もあります。
レッジョエミリア教育とシュタイナー教育

オーストリア出身の哲学者ルドルフ・シュタイナーが考案した教育方法です。出身はオーストリアですがシュタイナー教育が大きく知られていった場所はドイツです。
シュタイナー教育の理念としては、教育に使うものは全て芸術的な方法で学ぶということです。
余談になりますが、調べてみるとあの俳優の斎藤工さんは、新宿(現在は神奈川)にあるシュタイナー学園に小学校5年生まで通っていたそうです。

こう思われる方も多いと思います。事実、この二つの教育では、テストは無く、既存の教科書を使用しません。しかし、シュタイナー教育では、自分達でオリジナルの教科書を作成します。
シュタイナー教育では、「人は7年で成長過程が変わる」と考えています。
大きく成長するところが年齢よってあるという考えを持っています。
体の成長や芸術性、思考力や判断性など、年齢によって変わってくるのです。
さらにシュタイナー教育は3つの特殊な授業があります。
この一つ一つの授業の取り組む方法を、短期集中型で取り組ませていくほうが、子供の柔軟な頭にいいと考えています。そして心と体と頭のバランスがうまく調和されることが大切だと考えています。
この3つのバランスを整えるために、シュタイナー教育ではテレビがなく、キャラクターやCDなどがありません。
テレビを見るよりも、身体を動かして幼児期は過ごします。食べ物もオーガニック食品であったり、プラスチックのおもちゃを使わないといったちょっと特別なルールがあります。



もっとシュタイナー教育について学んでみたいと思われた方には、このような記事もおすすめです。
まとめ

いかがだったでしょうか?教育理論と言われるとなんだか難しく近寄りがたい感じがしますが、レッジョ・エミリアでは子どもひとりひとりの個性を奪わず、伸ばすことに重きをおいています。
日本との分化や環境の違いはあれど、「子ども」という存在は万国共通でその子が秘めている可能性も同じはずです。
全てが優れている子でなくても、その子の得意とする部分に着目し伸ばしていくことで、それが生きるための強みや武器になれば十分ではないかと私は改めて考えることができました。